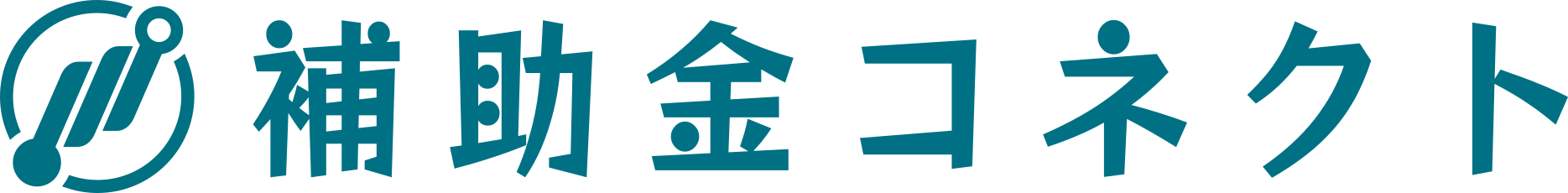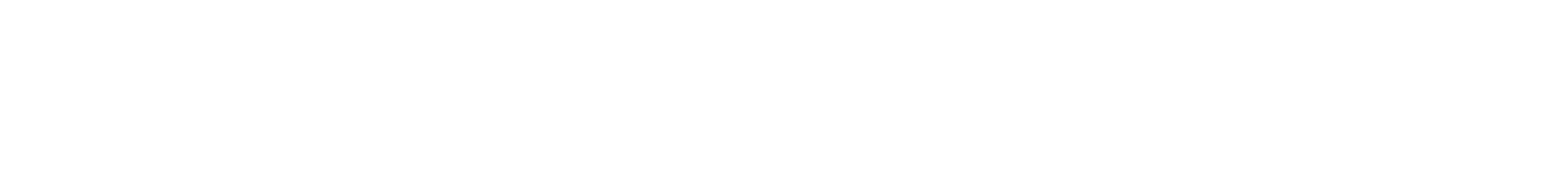事業譲渡における従業員への対処法とは?雇用契約や労働組合の注意点、事業譲渡契約のポイントを解説
事業譲渡は従業員の合意がないと成立しません。そのため、従業員に納得してもらうための対処法を知っておく必要があります。
この記事では、事業譲渡で従業員に説明すべき事項、および転籍を拒否する従業員への対処法、事業譲渡契約や雇用契約のポイントなどを解説します。
事業譲渡とは
事業譲渡とは、事業を営むのに必要な資産を譲渡企業から譲受企業に譲渡して、その事業を譲受企業が引き継ぐことです。事業を引き継ぐことが本質であり、単に資産を売却するだけの取引は事業譲渡とは呼びません。
事業を営むのに必要な資産とは、工場や店舗などの不動産、設備・在庫・備品などの物品、特許や商標などの無形資産などのことで、事業に必要なあらゆるものを含みます。
事業譲渡では、譲渡する事業で働く従業員を譲受企業に転籍させなければなりません。転籍は従業員の同意が必要なので、従業員に転籍を拒否されると事業譲渡が困難になります。これは株主の合意があれば成立する株式譲渡と大きく違う点です。
さらに、事業譲渡は必ずしも全ての従業員を転籍させるとは限らないので、転籍する従業員としない従業員をどのように選ぶか、および転籍しない従業員の処遇をどうするかといった問題も生じます。
このように、事業譲渡は従業員にまつわる問題が多く発生するM&Aスキームであり、従業員への対処法をきちんと押さえておくことが重要になります。
事業譲渡契約時のポイント
まずこの章では、事業譲渡契約締結時に押さえておくべき、従業員に関連するポイントを解説します。
雇用条件の悪化や急な変化は避ける
事業譲渡で従業員を転籍させる時、必ずしも雇用条件を以前と同じにする必要はありません。しかし、雇用条件が悪化すると、従業員の転籍拒否やモチベーション低下の原因になるため、悪化しないように契約内容を定めるのが原則になります。
雇用条件は給与面だけでなく、業務内容・労働時間・転籍後の地位なども含みます。たとえ給与面では問題がなくても、労働時間が長くなる、転籍後の地位が低下するなどの理由で、従業員に反対されないようにしなければなりません。
雇用条件はできるだけ変化させないのが望ましいですが、どうしても変えなければならない部分が出てくることもあります。
雇用条件の変化による離職を防ぐためには、たとえ最終的には雇用条件を変えるとしても、一定期間は変えない条項を事業譲渡契約に盛り込むのが有効です。一定期間は同条件で雇用して新しい環境に慣れてもらい、その後段階的に変えていくと受け入れられやすくなります。
転籍承諾書を提出してもらう
転籍承諾書(または転籍同意書)とは、事業譲渡にともなう転籍を従業員が承諾したことを書面で記したものです。事業譲渡契約時に転籍承諾書を添付することで、譲受企業は安心して契約を締結できます。
転籍承諾書を確実に提出してもらいたい場合は、提出しないと事業譲渡を実行できない旨を契約書に記載する(いわゆる「クロージング条件」に設定する)のも有効な手段です。
転籍拒否の従業員が出た時は譲渡価格を下げる
事業譲渡では必要な従業員が全て転籍できるようにするべきですが、どうしても転籍できない従業員が出てくるケースはあります。
転籍拒否の従業員が出てくることを想定して、転籍できない場合は譲渡価格を下げる契約にするのも有効です。特に、事業にとって不可欠な従業員が転籍できなかった場合は事業の価値が大きく下がるため、譲渡価格を下げることで調整する必要が出てきます。
従業員へ説明すべき事項
事業譲渡は従業員の同意がないと成立しないので、同意を得るために十分な説明をする必要があります。ここでは、具体的にどのような事項を説明すべきか解説します。
最低限説明すべき事項
厚生労働省が公開している「事業譲渡等指針」によると、従業員の承諾を得るためには、「事業譲渡に関する全体の状況」「債務の履行の見込み」「譲受企業の概要と労働条件」を始め、他にも必要な事項があれば適宜説明すべきとされています。
「債務の履行」とは、従業員に直接関係する退職金や未払い賃金などのことです。事業譲渡によって退職金が減ったり、未払い賃金が支払われないままになるのは従業員にとって受け入れがたいので、きちんと支払われる旨を説明しなければなりません。
従業員にとってのメリットを説明する
従業員の同意を得るためには、事業譲渡が従業員にとってどのようなメリットがあるか説明することが大切です。雇用条件や労働環境が改善される場合はそれをしっかり説明し、譲受企業に移ることでキャリアアップが目指せるなどのビジョンも説明するとよいでしょう。
従業員の心情面にも配慮する
雇用条件などの具体的な条件面だけでなく、心情面も十分に話し合うことが大切です。従業員は今まで働いてきた会社に愛着を持っていることが多く、たとえ雇用条件が良くなるとしても転籍したくないと言う従業員が出てくることも考えられます。
事業譲渡は、転籍の必要がない株式譲渡より大きな環境変化をともないます。環境変化は従業員に大きなストレスと戸惑いをもたらすので、離職やモチベーション低下が起こらないように十分話し合うことが大切です。
雇用契約を再締結する時のポイント
ここでは、事業譲渡で雇用契約を再締結する時のポイントを解説します。
雇用契約を再締結する時に重要なのは、退職金と有給休暇の取り扱いです。退職金と有給休暇は従業員が最も気になる点で、転籍の承諾やモチベーションに大きく影響します。
また、再締結には従業員の「真意による合意」が必要になること、特定の従業員の排除は無効になるケースがあることも押さえておきましょう。
退職金の取り扱い
転籍した従業員の退職金の取り扱いは、譲渡企業の退職金を払って清算するか、清算せずに譲受企業に引き継ぐかの2択になります。どちらの方法をとるにせよ、転籍のせいで退職金が減らないように配慮しなければなりません。
譲渡企業の退職金を清算する場合
譲渡企業で勤務した分の退職金を支払って清算する場合、勤続年数のリセットによって退職金が減らないようにしなければなりません。
例えば、譲受企業の退職金の計算方法が勤続年数によって増えるシステムの場合、転籍した従業員は譲渡企業での勤務年数が考慮されず損をする可能性があります。この場合の対処法としては、勤続年数を譲渡企業と通算して退職金を計算したうえで、譲渡企業がすでに支払った退職金額を差し引くといった計算方法が考えられます。
退職所得の控除についても注意が必要です。退職所得は勤続21年目から控除額が増えるので、例えば譲渡企業で15年、譲受企業で15年勤務した場合、転籍せず譲渡企業で30年勤務した場合より控除額が少なくなります。
転籍のせいで控除額を損しないための対処法としては、勤続年数を通算して控除額を計算したうえで、譲渡企業の退職金支払時にすでに控除された額を差し引くといった方法が考えられます。
清算せず譲受企業に引き継ぐ場合
譲渡企業の退職金を清算せず譲受企業に引き継ぐ場合は、譲渡企業の退職金の額を事業譲渡の譲渡金額から差し引かなければなりません。差し引いておかないと、譲渡企業の退職金を譲受企業が負担することになってしまいます。
引き継いだ退職金は譲渡企業のルールに従って計算し、その後の分は譲受企業の規定に従います。もちろん、勤続年数は通算でカウントする必要があります。
有給休暇の取り扱い
転籍すると、譲渡企業の未消化の有給休暇は原則として消滅します。消滅すると従業員は不満を持つ可能性が高いので、事業譲渡契約書に有休を持ち越す旨を盛り込んでおくとよいでしょう。
有給休暇を買い取って清算することは原則として認められませんが、退職時は例外として買取できます。
「真意による合意」が必要
雇用契約の再締結には従業員の合意が必要ですが、これは従業員が本心から納得する「真意による合意」でなければなりません。
脅しなどの行為で無理やり合意させたり、嘘の雇用条件などを提示してだまして合意させる行為は厳禁です。民法第96条で「詐欺や脅迫による合意は取り消すことができる」と定められているので、従業員が取消を求めた場合は取り消すことができます。
特定の従業員の排除は無効になるケースがある
事業譲渡でどの従業員を雇用するかは自由に決めることができますが、目ざわりな従業員の排除など不当な目的で雇用を拒否する行為は、無効とする判例があります。特定の従業員と雇用契約を締結しない場合は、公平で正当な理由がなければなりません。
労働組合員の排除を目的として、組合員でない従業員だけを雇用するのが典型的なケースです。平成14年の「青山会事件」や平成21年の「吾妻自動車交通の事件」では、事業譲渡にともなって組合員を排除しようとした譲受企業に対して、組合員の解雇を無効とする判決が下されています。
転籍できない従業員への対処法
十分な説明と協議をした結果、それでも転籍できない従業員がいる場合は、転籍は断念して別の手段を検討しなければなりません。
転籍できない従業員の処遇は、以下の4つのいずれかになります。
譲渡企業の他の部署で働いてもらう
出向の形で譲受企業で働いてもらう
希望退職を募る
整理解雇する
譲渡企業の他の部署で働いてもらう
転籍できない従業員に対してまず検討すべきなのは、譲渡企業の他の部署への配置転換です。
配置転換は転籍ほどではないにせよ、従業員にとって大きな環境変化となります。従業員はストレスや不安を感じるので、安心して働けるように配慮しなければなりません。
元の部署と似た部署への配置転換なら、これまでのキャリアも生かせるので働きやすいでしょう。また、肩書を落とさないようにするのもモチベーション維持のためには大事です。
出向の形で譲受企業で働いてもらう
配置転換できる部署がない場合は、譲渡企業に籍を置いたまま譲受企業に出向してもらう手段もあります。最初は転籍に反対していた従業員でも、出向して譲受企業に慣れてくると合意してもらえることもあります。
労働契約法第14条で不当な出向は無効とする規定があるので、出向してもらう際は規定に沿っているか確認しなければなりません。具体的には、「出向が業務上どうしても必要であること」「出向する従業員の選び方は合理的であること」「出向によって従業員が労働条件・日常生活で不利益を被らないこと」などが条件となります。
希望退職を募る
配置転換も出向もできない従業員に対しては、希望退職を募って自主的に退職してもらうよう促すことになります。転籍や出向を拒否したことだけを理由に解雇するのは解雇権の濫用になるので、まずは従業員の意思で退職できるよう試みなければなりません。
希望退職に合意してもらうためには、退職金を割り増ししたり再就職のサポートをするなど、従業員にとってメリットのある条件を提示する必要があります。
整理解雇する
希望退職にも合意してもらえなかった場合は、最終的な手段として整理解雇を検討することになります。
労働契約法第16条では、「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」でないと解雇はできないと定められているため、解雇は慎重に行わなければなりません。事業承継等指針にも、転籍を拒否したことのみを理由に解雇するのは、社会通念上相当とは認められない旨の記載があります。
何をもって「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」であるとみなすかの判断基準については、これまでの判例によって確立された「整理解雇の4要件」というものがあります。
整理解雇の4要件は以下のとおりです。
経営上どうしても整理解雇が必要である
整理解雇以外の手段を十分に行った
解雇する従業員の選び方が合理的である
従業員および労働組合と十分協議した
整理解雇においても希望退職の時と同様、退職金の増額や再就職サポートなどを行うことで、従業員に納得してもらいやすくなります。
労働組合との協議における注意点
事業譲渡では、従業員だけでなく労働組合とも十分な協議・説明を行う必要があります。労働組合とのトラブルは訴訟につながることも多いため、注意点をきちんと押さえておくことが大切です。
協議のタイミングと回数
事業譲渡等指針によると、労働組合との協議は、従業員と個別に協議する前の段階で行うべきとされています。さらに、その後も必要があれば適宜協議するべきとされています。
交渉申し入れは原則拒否できない
労働組合は労働組合法第6条で団体交渉権が認められているので、交渉の申し入れをされたら会社側は原則として応じる必要があります。たとえ従業員と個別に協議したとしても、それを理由に団体交渉を拒否することはできません。
譲受企業も交渉に応じなければならないことがある
まだ雇用契約を結んでいない事業譲渡締結前の譲受企業も、譲渡企業側の労働組合との交渉に応じなければならないケースがあります。
過去の判例によると、譲渡企業の従業員に対して支配・決定権を持っているとみなされる場合や、譲渡企業の従業員を雇用する見込みがある場合は、譲受企業も団体交渉に応じなければならないとされています。
まとめ
事業譲渡は従業員の合意がないと成立しないので、十分な協議と説明を行う必要があります。
従業員や労働組合に何を説明すればよいか、事業譲渡契約書に何を盛り込むべきかなどを理解して、トラブルなく事業譲渡が進められるようにしましょう。
トラブルになると対処が難しくなるため、事前に専門家に相談することをおすすめします。