早期経営改善計画とは?概要や対象者、メリット、活用の流れを解説
新型コロナウイルスや物価高、ウクライナ情勢などの影響により、経営上ダメージを受けている日本企業は少なくありません。
実際にコロナウイルス以降、廃業に追い込まれた企業も多いですが、そうなる前に活用したいのが早期経営改善計画です。
本計画を策定することで、経済的補助を受けながら外部専門家による経営に関する質の高いアドバイスをもらうことができます。
この記事では、早期経営改善計画の概要とメリット、活用の流れについて解説します。
早期経営改善計画とは

早期経営改善計画とは、経営改善を目指す中小企業と専門家の取り組みを支援する制度です。
本制度は、2017年度から始まった中小企業庁管轄の事業で、経営改善を図る中小企業等が、専門家による支援を受ける際にかかる費用の2/3が補助されるものです。
資金面で苦しい中小企業の事業者でも、この制度を活用すれば、経営に関する悩みや不安を専門家にお得に相談することが可能となります。
対象者
本事業の支援対象者は中小企業・小規模事業者で、個人事業主も含まれます。
ただし、開業から1年以上の営業を経た決算の実績がない事業者は対象外です。
さらに、以下の事業者も対象外となります。
<対象外となる事業者>
社会福祉法人
特定非営利活動法人
一般社団法人
一般財団法人
公益社団法人
公益財団法人
農事組合法人
農業協同組合
生活協同組合
LLP(有限責任事業組合)及び学校法人
上記以外にも支援対象とならない法人形態や業種がありますので、事前に専門家や中小企業活性化協議会に確認しておきましょう。
早期経営改善計画のメリット
早期経営改善計画を策定することのメリット
資金繰りを改善できる
中小企業の経営者は、目の前の売上や売掛回収、社内外の問題解決に日々忙殺されており、「数か月先の資金繰り」にまで気が回らないケースが少なくありません。
資金繰りを計画的に行えないと、最悪の場合、黒字倒産してしまう可能性もあります。早期経営改善計画を策定することで資金繰りが可視化され、財務上のリスクを事前に回避できるメリットがあります。
攻めの経営が行える
早期経営改善計画は、「攻めの経営」のための事業シミュレーションにも役立ちます。
例えば大規模な設備投資を検討されている場合、早期経営改善計画において投資後の収支や資金繰りのシミュレーションを策定しておくことで、安心して事業にチャレンジできます。
資金繰りに関する不安が解消されると、事業投資に前向きになれるほか、経営や事業において新たな展望が開けるなど、会社全体にも良い影響をもたらします。
金融機関との対話のツールになる
「金融機関との対話のツールが手に入る」ことも、早期経営改善計画の大きなメリットです。こちらはあまり知られていない隠れたメリットになりますので、詳しく解説します。
借入を行う際、金融機関に相談されると思いますが、金融機関の担当者は1人で100社以上の事業者を担当しているケースがよくあります。そのため、個々の会社の事業内容や決算状況を細かく把握していないことが一般的です。そのような状態で融資を申し込んだとしても、よくわからない会社への貸付条件は厳しくなる傾向にあります。
一方、早期経営改善計画を策定しておくと、自社の経営分析や資金繰りの実績と今後の見通しまでを、金融機関担当者が理解しやすい形で資料化することになります。通常、融資を受けるために早期経営改善計画のような精緻な資料を作成する事業者は限られますので、金融機関の担当者の記憶に残りやすく、行内で稟議にあげていただく際にも当計画をご活用いただけることでしょう。
結果として、事業者側に有利な借り入れ条件を引き出すことができる可能性があります。他にも、金融機関の担当者と関係を深めることで、早期改善計画を策定するために使った費用以上のメリットを回収できる可能性もあります。
費用面のメリット
本事業では、外部専門家の支援を受ける際の費用の一部を負担してくれます。
補助率は2/3ですが、補助対象経費毎に、以下の表の通り上限額が設けられています。
補助対象経費 | 上限額 |
|---|---|
計画策定支援費用 | 15万円 |
伴走支援費用<期末> | 5万円 |
伴走支援費用<期中> | 5万円 |
※金融機関交渉に係る費用は10万円を上限として加算できます。
補助の対象となれば、専門家への相談料を抑えることができます。
例えば、過去の資金繰りを分析して将来の資金計画を策定する資金繰表(実績・計画)の策定や、損益計画の立案、経営課題と解決など、事細かく自社の問題を相談しやすくなります。
日本国内にある企業の99%は中小企業と言われており、中小企業は日本経済を支える存在です。
政府としても、中小企業が廃業すると、雇用が失われ経済にも悪影響が出る懸念があることから、全面的に支援してくれる特徴があります。
早期経営改善計画の流れ
ここでは早期経営改善計画の流れについて紹介します。
金融機関に相談する
早期経営改善計画ではさまざまな書類が求められ、書類を作成するにあたっては金融機関の「事前相談書」が必要です。
事前相談書は、金融機関へ相談した事実を証明するための書類になります。
事前に、最寄りの金融機関や、過去に取引して相談しやすい銀行などに相談しましょう。
認定支援機関に相談する
金融機関へ相談するのと同時に、国が認定した税理士や中小企業診断士などで構成されている認定支援機関(外部専門家)へも相談します。
連名で書類を作成したり、申請する必要があるため、経営者一人で進めないように注意してください。
認定支援機関は中小企業庁の「認定経営革新等支援機関検索システム」で調べることができます。
相談時には、対象者の要件を満たしていこと等の確認をし以下の書類を準備する必要があります。
早期経営改善計画策定支援事業利用申請書
申請者の概要
業務別見積明細書
履歴事項全部証明書
認定支援機関の認定通知
事業者に対する認定経営革新等支援機関の見積書及び単価表
金融機関の事前相談書
申請者の直近3年分の申告書
上記の書類は申請時に必要となり、外部専門家と連名で経営改善支援センター事業へ提出する流れとなります。
経営改善支援センターに利用申請する
認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業利用申請書」と「事前相談書」を提出します。
また、金融機関自体が認定支援機関として認定されている場合は、金融機関が連名で申請することもできます。
早期経営改善計画の策定し提出する
書類の提出が完了した後は、外部専門家と早期経営改善計画の策定を行い、金融機関へ提出します。
策定時には、ビジネスモデル俯瞰図の作成や資金繰りの見直しなど、経営に関する課題を明確かつ具体的にプランニングすることがポイントです。
あまりに無理な策定の場合、申請が否認される可能性もあるため、現実的な策定を行うようにしましょう。
また、金融機関にも早期経営改善計画書を提出し、「受取書」を発行してもらうようにしましょう。
支払いの申請を行う
支払い申請をしない限り経営改善支援センターから費用を支払われることはありません。
申請は認定支援機関と一緒に行う必要があり、なおかつ以下の書類を用意します。
受取書
経営改善支援センター事業(早期経営改善計画策定支援)費用支払申請書
外部専門家の請求書類
申請者と外部専門家が締結する早期経営改善計画策定支援に係る契約書
振込受付書や払込取扱票
申請後は、認定支援機関に対して計画策定費用の2/3が支払われる仕組みとなっているため、残金分を支払う必要があります。
モニタリング報告書を提出する
計画策定の1年後の決算期に、認定支援機関より進捗を確認するモニタリングが実施されます。
モニタリングを受ける際は、支払申請終了後に、以下の書類を提出しなければいけません。
モニタリング費用支払申請書(早期経営改善計画策定支援)
申請者と外部専門家が締結するモニタリングに係る契約書
外部専門家の請求書類(支援センター宛)
振込受付書や払込取扱票
上記の書類とモニタリング報告書を認定支援機関より、経営改善支援センターに提出します。
なお、モニタリング費用の上限は、期中・決算期いずれも5万円です。
まとめ
早期経営改善計画とは、経営改善を目指す中小企業と専門家の取り組みを支援する制度で、補助対象経費に合わせて、最大25万円が補助されます。
そのため、専門家への相談料のコストを抑えて経営改善に関する悩みや問題解決に役立たせることが可能です。
本制度を利用するためには、専門家や金融機関との連携が重要となるため、普段から利用している税理士や銀行などに相談するところから始めてみると良いでしょう。
補助金コネクトでも、早期経営改善計画のご支援を行っております。経営や資金調達に関するサポートも行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
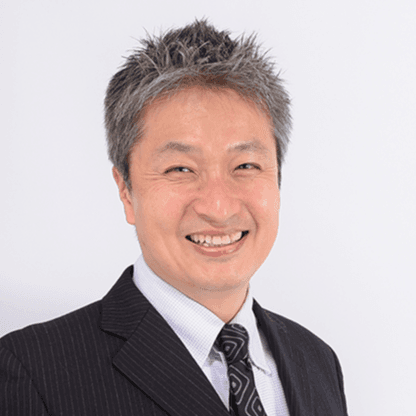
代表取締役 西村佳隆







